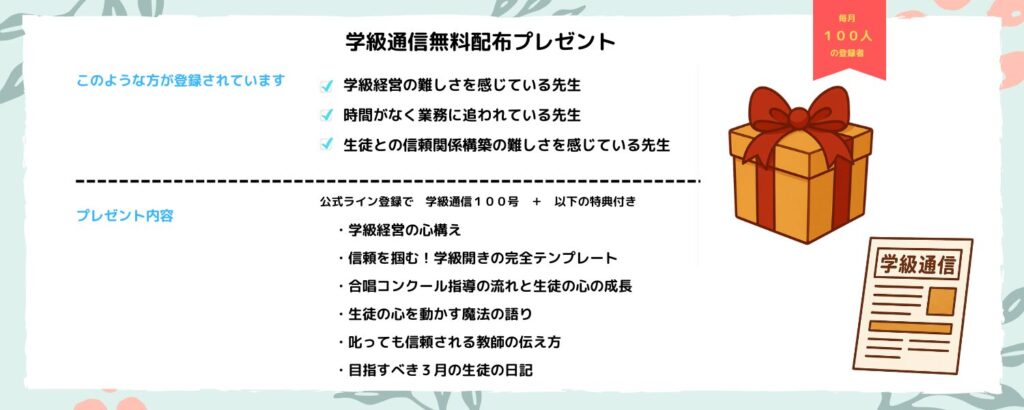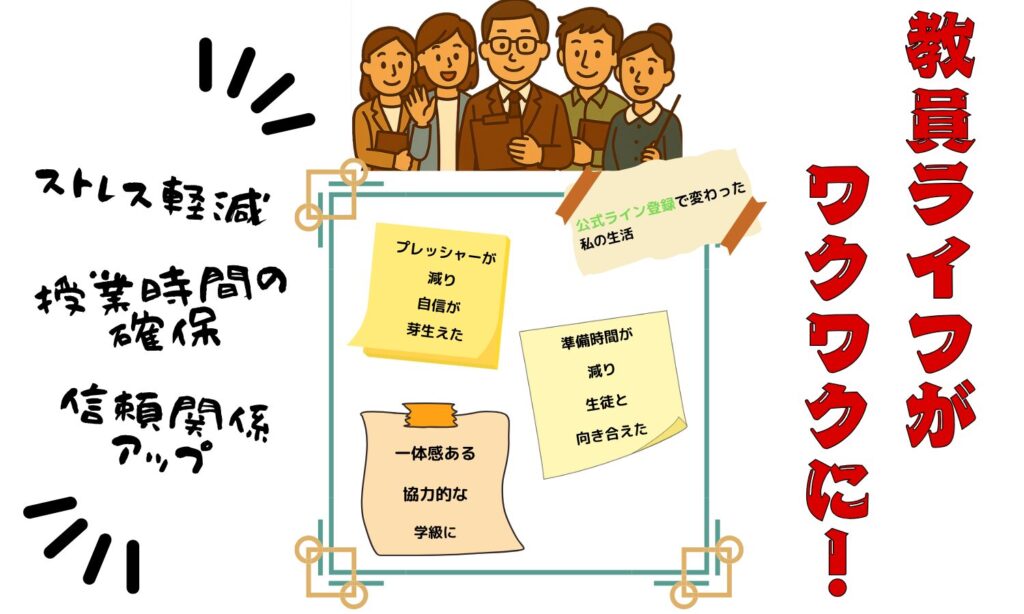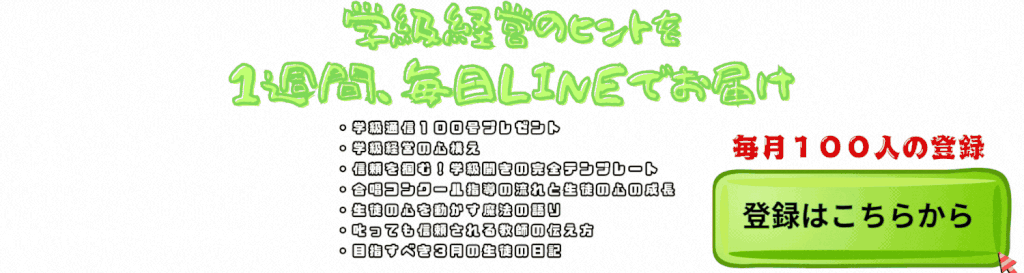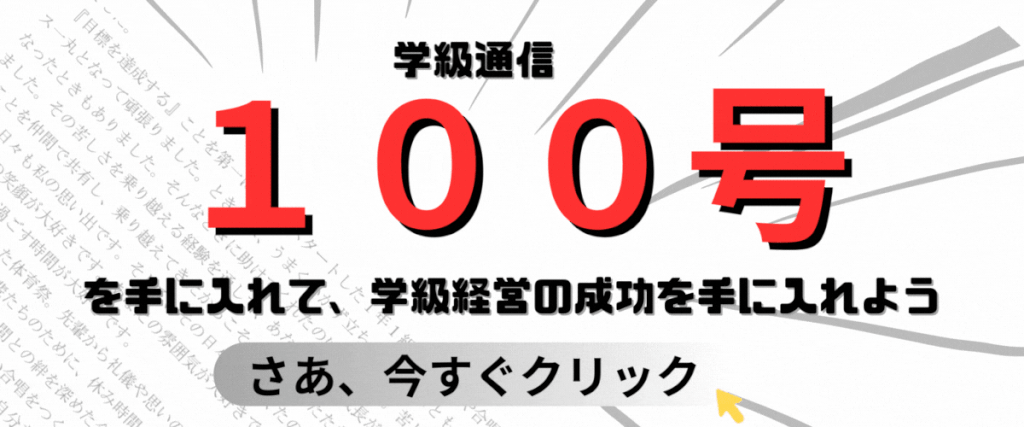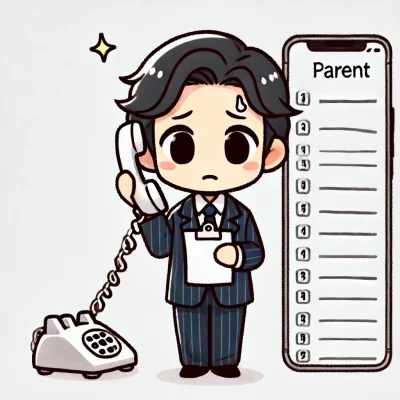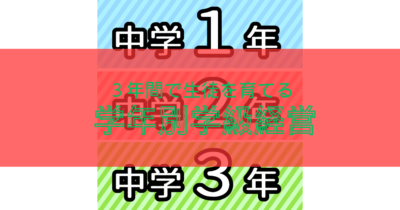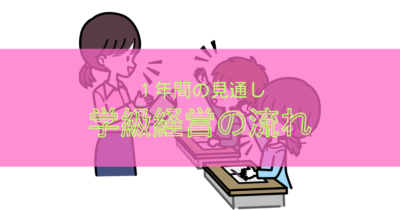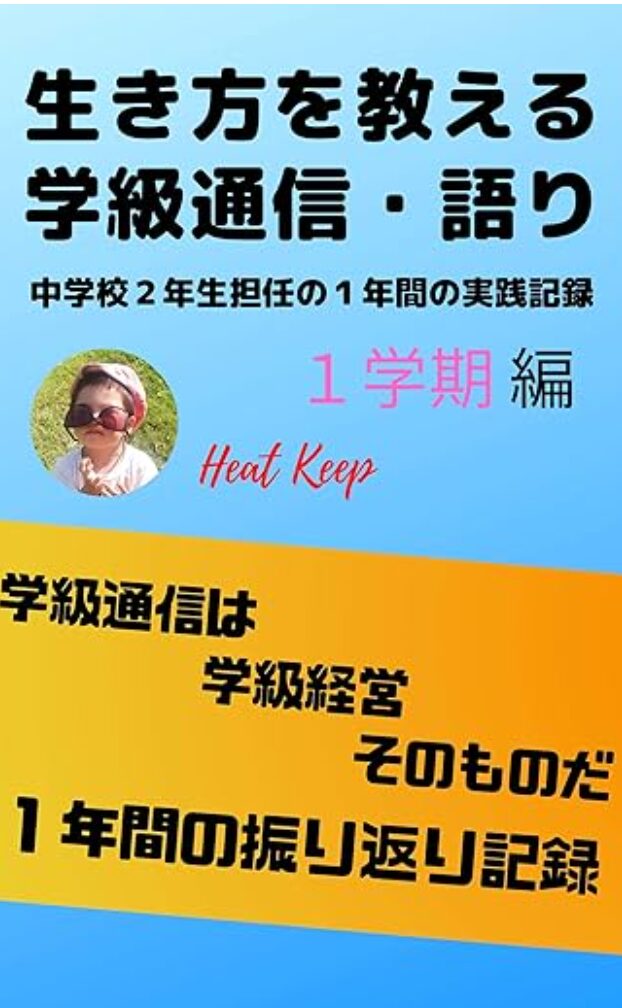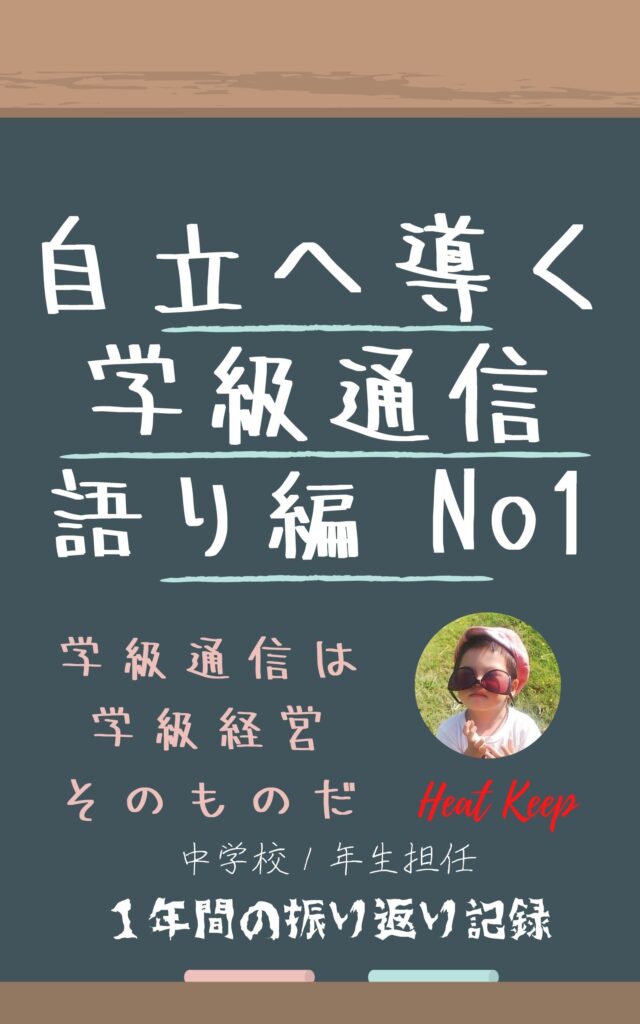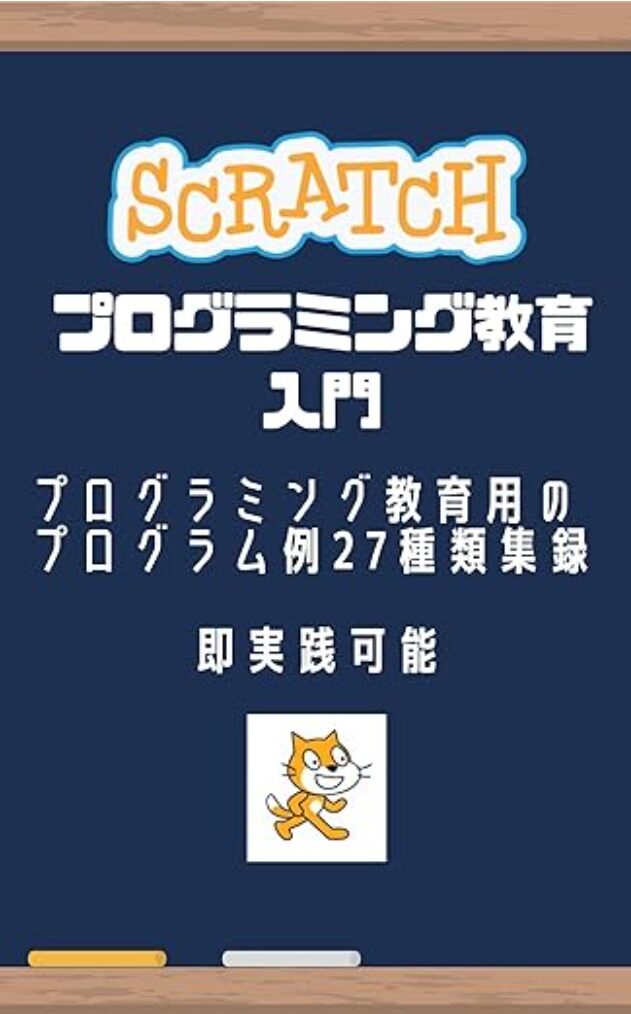はじめに
合唱コンクールは多くの中学校で行われるイベントですが、教師にとっては準備や指導に多くの課題が伴います。
生徒のモチベーションを保ちながら、全員が一丸となって最高のパフォーマンスを引き出すにはどうすれば良いのでしょうか。
この記事では、合唱コンクールを成功させるための具体的なポイントを紹介します。
計画段階から練習方法、当日の運営に至るまで、実践的なアドバイスを提供します。
この記事を読み終える頃には、合唱コンクールの成功に向けた具体的な手順と、実践可能なテクニックを理解し、自信を持って生徒たちを指導することができるようになります。
クリックできる目次
合唱コンクールの目的と目標
合唱コンクールを成功させるためには、まず目的と目標が重要です。
以下のポイントを押さえて、しっかりと準備を進めましょう。
合唱コンクールの目的
合唱コンクールの目的
ここが一番重要です。
目的なくして、行事に価値は出ません。
つまり、目的が達成されれば、行事の勝敗はどちらでもよいのです。
では、合唱コンクールの目的とは一体何でしょうか?
それは、
合唱コンクール前と合唱コンクール後で生徒たちがどのように変容したか
です。
変容なくして、合唱コンクールの価値はありません。
合唱コンクールに限らず、変容がなければ、行事の価値はありません。
行事は、あくまで手段です。
技量を高めることが目的になってはいけません。
生徒の変容、つまり、日常生活の向上が大切なのです。
行事は、生徒の変容が大前提です。
目標設定
まず、合唱コンクールの目標を明確にしましょう。
これにより、生徒たちのモチベーションを高め、全員が同じ方向を向いて努力できるようになります。
そして、目標は、教師と生徒を分けて設定します。
生徒の目標は、最優秀賞を獲ることにこだわっても良いでしょう。
競争を通じて努力することで、集中力やチームワークが養われます。
勝ちを目指すことで、得られるものは大きいです。
しかし、合唱コンクールの目的が、生徒の変容や日常生活の向上にあることを忘れてはいけません。
そのため、教師の目標は、単に最優秀賞を目指すだけでなく、生徒たちが日常生活の中で成長し、変容するためのサポートをすることです。
具体的には、以下のような目標を設定すると良いでしょう。
- 協力とチームワークの強化: 生徒同士が協力し合い、互いに助け合う姿勢を育てる。
- コミュニケーション能力の向上: 歌を通じて、自分の意見や感情を他者に伝える力を養う。
- 自信と自己肯定感の向上: 合唱の練習や本番を通じて、自分に自信を持ち、自己肯定感を高める。
- 責任感の育成: 各自の役割を果たし、全体の成果に貢献する責任感を持たせる。
このように、教師と生徒の目標を明確にし、各自がそれぞれの立場で最善を尽くすことで、合唱コンクールの目的である生徒の変容と日常生活の向上が達成されるでしょう。
合唱コンクールの練習初日には、過去の合唱コンクールの動画を見せると良いでしょう。
スタートの時点で、生徒たちにゴールを意識させることが重要です。
「合唱コンクールに向けて本気になった生徒の日記」を参照してください。
合唱コンクールは4月からの積み重ね
上記の教師の目標を見てわかるように、これらは普段から意識して取り組んでいる項目だと思います。
合唱コンクールは、10月や11月に実施される学校が多いです。
つまり、合唱コンクールは、4月から積み上げてきた生徒の成長を、より次元の高いレベルまで引き上げる行事ということです。
さらに言えば、4月からの積み上げがなければ、合唱コンクールの成功は小さなものにとどまってしまうでしょう。
日々の積み重ねが大切であり、これがなければ合唱コンクールでの真の成長や変容は望めません。
行事の指導として大切なことは、
行事の成功 ⇔ 日常の向上
が相互にからみ合っていることを意識することです。
日常から生徒の成長を促しておけば、行事での学級経営はきっと成功するでしょう。
また、行事で生徒を成長させることで、日常生活も向上していくはずです。
このように、日常と行事は相互に関連し合い、互いに成長を促す役割を果たします。
日常の授業や活動を通じて生徒の基礎力を育て、それを行事での経験でさらに引き上げる。
このプロセスを繰り返すことで、生徒たちの成長は加速し、学級全体の雰囲気は向上します。
行事は単なるイベントではなく、日常の学びを実践する場であり、生徒たちが自分たちの成長を実感する重要な機会です。
そのため、日常の取り組みがしっかりしていれば、行事も自然と成功し、さらに大きな成果を生み出すことができるのです。
合唱コンクール前日に書いた生徒の日記
合唱コンクールの目標を達成した生徒たちの日記です。
先輩の日記(合唱コンクールに向けて本気になった生徒の日記参照)の「4組の世界」という言葉がめっちゃ印象に残ります。
日常でもそうだけど行事とか他のクラスを意識することが多くなると思います。
お互いを高め合っているから、他のクラスを意識することも大事だと思いますが、やっぱり一番は自分たち。
自分たちの目標にちゃんと進んでいるか、自分たちの歌に合った合唱にできているかなど。
本番って前にはめっちゃたくさんの人たちがいて、やっぱり周りの人たちのことを考えてしまいます。
周りばっか気にして思うような合唱ができないとか嫌です。
だったらもう観客がいないつもりまでとはいかないけど、とにかく体育館全体を1-1の世界にしてしまえばいいと思います。
歌っていたら、周りの人も私たちと笑顔になってしまうくらい、一緒に歌ってしまうくらいみんなを引きつける歌を歌い、体育館を1-1で支配したいです。
そのためには今やっている表現力が大事だと思います。
3年生の歌を聴いているとき、他の人の表情とかも見ていたけど、やっぱり●●先輩の方にどうしても目がいってしまいます。
歌ももちろん上手だけど、歌とか関係なくどうしても●●先輩に目がいってしまいます。
あの表現を1-1でも全員がやったら絶対みんな1組の世界に入ってしまうと思います。
合唱コンまであと1日。
まだまだよくなります。
常に上を目指して終わった後、達成感がこみ上げてくる合唱にしたいです。生徒の日記
最初はこれほどに熱く楽しくなれる行事とは思っていませんでした。
リーダーのことを陰で言ったり、練習の空気が悪くなることも多くて、乗り越えられるか不安なことも多かったです。
本音の話し合いをしたとき、また雰囲気が悪くなるのではないかと思った時もあったけど、逆にもっと頑張ろうってなっている人もいて当たり前のことだったかもしれないけど、みんな温かいなって感じられました。
最近この歌を歌っていると自然と笑顔になってきます。
「この広い世界の中で~Wiht You Smile」のところを歌っているときとか、1-1の仲間と出会えてよかったと思うし、個人的に出会えてよかったと思う人がいて、そういう人たちのことを考えながら歌うとなんかほっこりします。
あと、合唱コンってこんないい行事なんだなって思えます。
本番、歌っている人には周りの人にも私たちの歌に入り込んでもらいたいし、私と同じように、出会えてよかったな、この人と一緒にいれてよかったなとか思い出して、笑顔になってもらいたいです。
今まで大変だったろうに、いつもみんなを引っ張ってくれたリーダーたちには本当に感謝です。
ちょっと早いかもしれないけどありがとう。
こんなに最高な行事が1年に1回しかなくて、3年間あるうちのの1回がもう終わってしまいます。
聴いている人全員に笑顔を届けるつもりで、絶対に悔いのないめっちゃいい合唱にします!生徒の日記
今日が本番前日の最後の練習でした。
そのときに私が思い浮かべていたのは、このクラスの仲間のことでした。
私がこの合唱で伝えたい相手は聴く人は当たり前なのですが、とにかく仲間です。
理由はこのクラスの仲間が大好きだからです。
私たちは相手を信じることができています。
だから合唱のときに「ここはこうした方がよいよ」とか「音程がわかる?」とか「そこよいよ」とか言い合うことができます。
そんなことを言い合える、心から信じ合えるそんな仲間が私は大好きです。
そして、そんな大好きな仲間と「この広い世界の中でめぐりあえた」きせきや喜びなどを歌で伝えたいです。
そして、その喜びなどを思い浮かべ、その上に仲間への感謝の気持ちを込めて、明日も歌いたいです。
話が少し変わりますが、笑顔ってすごいなと今日改めて思いました。
5時間目の最初に1曲通して歌ったのですが、「まだ少し顔が怖い」と言われていました。
そこで、A男くんが変顔をときどきするように言われていました。
その顔でみんなが笑顔になりました(笑)。
まあ結局変顔はしてくれなかったのですが、最後に歌ったとき、初めの方で笑いが止まらなくなりました。
A男が変顔をした訳ではなかったのですが、あまりにもにこにこしていたので、みんなが笑い始めて最初だけはちゃんと合唱になっていなかったです(笑)。
でも、何がすごいかと言ったら、笑顔が移るということです。
一人が笑い出すと、みんな笑い出します。
それだけ笑顔の影響力がすごいということです。
本番で、笑いすぎるのは絶対だめなんですけど、それでもにこにこしながら歌えるようにしたいです。生徒の日記
効果的な練習方法
合唱コンクールに向けた練習は、ただ歌うだけでなく、計画的に進めることが重要です。
以下の方法を取り入れて、効果的な練習を行いましょう。
以下の投稿は、ぜひ一度ご覧ください。
基礎練習
発声練習やストレッチなど、基礎的なトレーニングを毎回の練習に取り入れることで、生徒たちの歌唱力を向上させます。
パート練習
各パートごとに練習を行うことで、ハーモニーを整えるとき、自分のパートに自信を持たせます。
全体練習
全員での練習を定期的に行い、全体のバランスや表現力を確認します。
また、指導者が指示を出しやすい環境を整えましょう。
フィードバックの工夫
学級で行う練習は、上記のとおりです。
いたって、どの学校でも行う練習方法だと思います。
しかし、大切なことは、どのように生徒へフィードバックをするかどうかです。
フィードバックをする上で重要視することは、生徒に見える化させることです。
つまり、数値化することです。
- 家で何回音源を聞いたか尋ねる
- 各パートに点数をつける
そして、目指すべき回数の基準を明確にしたり、どうしてその点数をつけたのか理由をつけたりすれば、生徒の合唱は伸びていきます。
次は、合唱指導の順番を紹介します。
合唱指導のステップ
1. 個人で音合わせ
合唱の基本は、まず個人で正確な音程を取ることから始まります。
各生徒が自分のパートの音程をしっかりと確認し、耳に馴染ませることが重要です。
ピアノや音源を使って、自分の声が正しい音程に合っているかを確認しましょう。
そして、自主練習を促すために、各生徒に練習用の音源を提供すると良いでしょう。
スマートフォンやタブレットを使って音源を再生し、耳で覚えながら練習することで、正確な音程を身につけることができます。
2. 互いに向かい合って音合わせ
生徒同士が向かい合って音合わせを行います。
これにより、お互いの声を聞き合いながら微調整を行うことができます。
ペアで練習することで、互いのフィードバックを受け取り、音程を修正することができます。
3. パート練習
個人の音程がしっかりと確立されたら、次はパートごとに練習を行います。
同じパートの生徒が集まり、互いの声を聞きながら練習することで、パート全体の音程が整います。
ここでは、指導者が各パートのバランスをチェックし、必要に応じて指導を行います。
4. 全体練習
各パートが安定した音程を取れるようになったら、全体練習に移ります。
まず、他のパートにつられないといったことが重要になります。
そして、合唱全体のバランスを確認します。
この段階では、各パートが他のパートとどう調和するかを意識しながら歌います。
全体練習では、合唱の総合的な音楽性を高めることが目標です。
表現力やダイナミクスを意識しながら練習を行い、曲全体の完成度を上げていきます。
5. 一人一人の間隔をあける
全体練習で音程が安定してきたら、一人一人の間隔をあけて練習を行います。
間隔を広げることで、音が分散し、各自が自分の音をしっかりと出さなければならなくなります。
これにより、個々の声がより明瞭に聞こえ、各自が自分の音程を維持する能力が試されます。
また、広がった配置により、合唱全体の音の広がりや響きを体感することができます。
6. 歌詞の意味を考えながら歌う
合唱の最終段階として、歌詞の意味を考えながら歌う練習を行います。
歌とは、相手に訴えるものです。
歌詞の内容を深く理解し、それに基づいた表現力を養うことが重要です。
各生徒が歌詞の感情や物語を理解し、それを声に乗せて伝えることができるように指導しましょう。
特殊な練習方法
運動場などの広い場所で歌う
運動場などの広い場所で練習を行います。
よいリフレッシュとなることでしょう。
また、広い場所で歌うことで、声の響きや音の広がりを実感し、本番に備えることができます。
階段で歌う
階段での練習は、各階ごとにパートごとに分かれて歌うことで、各パートの独立性と調和を同時に育む方法です。
一階にはソプラノ、二階にはアルト、三階にはテノール、四階にはバスといった具合に、各階ごとに異なるパートが配置されます。
各階でパートごとに練習し、声の響きを確認しながら階段を利用することで、音の広がりやバランスを調整します。
この方法は、パートごとの声がどのように一体となって合唱全体を支えるかを理解するのに非常に役立ちます。
仰向けになっておなかを押さえて歌う
仰向けになっておなかを押さえて歌う練習は、正しい腹式呼吸を身につけるために非常に効果的です。
仰向けの状態で腹部に手を置き、呼吸をコントロールすることで、声を安定させ、力強い発声が可能になります。
この方法は、特に初心者にとって有益で、正しい呼吸法を体得するのに役立ちます。
指揮者や伴奏者、パートリーダーのサポート方法
指揮者や伴奏者、パートリーダーには大きな責任が伴います。
リーダーは、指示を出す立場でありながらも、孤立しやすいという問題があります。
リーダーが円滑に役割を果たせるようにするための具体的なアドバイスと、効果的なサポート方法についてご紹介します。
リーダーの孤立を防ぐためのサポート方法
リーダーはその立場上、指示を出す役割を担っているため、周りからのプレッシャーや孤立感を感じやすいです。
このため、教師はリーダーが孤立しないようにサポートすることが重要です。
周囲とのコミュニケーションを促進する
リーダーが他の生徒と円滑にコミュニケーションを取れるよう、以下の方法を試してみましょう。
定期的なミーティングを設ける
リーダーと他のメンバーが意見交換できる場を設けることで、相互理解を深める。
チームビルディング活動
練習の合間にリーダーシップゲームやグループ活動を取り入れる。
感謝と評価を伝える
リーダーの努力を認め、感謝の意を伝えることも重要です。
生徒の頑張りを認めて、認めて、認めていきましょう。
学級の前で褒める
全員の前でリーダーの努力を称賛する。
個別に褒める
個別に話し合い、リーダーの頑張りを認める。
学級通信で褒める
学級通信に、リーダーの頑張りを掲載する。
朱書きで褒める
日々生徒が書いてくる日記に、朱書きをして褒める。
音楽的な指導とアドバイス
リーダーが曲を理解し、適切に指導できるようにするためには、教師のサポートが欠かせません。
曲の解釈と指示の仕方
リーダーが、声の強弱や音楽記号に注意しながら歌うポイントを用紙にまとめさせます。
リーダーに熱が入ってくると、楽譜が真っ赤になります。
大量のポイントが書きなぐられるからです。
その楽譜をぜひ、学級の仲間に見せてあげましょう。
リーダーの頑張りが、仲間に認められると思います。
リーダーの指導力を伸ばすための練習
リーダー自身が成長できるよう、指導力を伸ばすための練習も取り入れます。
リーダーに指導の機会を与える
リーダー自身が指導する場面を設け、教師はそれを見守りながらアドバイスを行う。
フィードバックの提供
練習後にリーダーに対して具体的なフィードバックを提供し、改善点を明確に伝える。
練習スケジュールとメニューの策定
合唱練習を効率的に進めるためには、スケジュールとメニューの策定が必要です。
必要があれば、生徒に以下の内容をアドバイスしてあげてください。
スケジュールの作成
効果的な練習スケジュールを作成するためのポイントは以下の通りです。
目標設定
練習の最終目標と中間目標を設定し、それに向けたステップを明確にする。
時間配分
各練習の時間配分を工夫し、効率的に練習を進める。
練習メニューの考案
バランスの取れた練習メニューを考案し、実施します。
ウォームアップ
声を出す前のウォームアップエクササイズを取り入れる。
パートごとの練習
パートごとに分けて詳細な練習を行う。
全体練習
最後に全体で合わせる練習を行い、調和を確認する。
問題解決とストレスマネジメント
リーダーは多くの責任を負うため、ストレスや問題に直面することが多いです。
教師はこれらをサポートする役割を果たします。
問題解決のサポート
リーダーが困ったときに適切なアドバイスを提供します。
オープンドアポリシー
リーダーがいつでも相談できる環境を整える。
問題の早期発見と対応
リーダーの様子を観察し、問題が発生しそうな場合には早めに対応する。
ストレスマネジメント
リーダーがストレスを軽減できるようサポートします。
リラックス法の紹介
深呼吸やストレッチなど、簡単にできるリラックス法を教える。
休憩時間の確保
練習の合間に適度な休憩時間を設ける。
一番は、教師がリーダーの理解者になる
ことです。
合唱コンクールのおすすめの曲
生徒たちが楽しんで歌える曲を選ぶことが大切です。
また、曲の難易度や歌詞の意味も考慮しましょう。
1年生におすすめの曲
Believe
杉本竜一が作詞・作曲したこの曲は、希望と勇気をテーマにしています。
翼をください
山上路夫が作詞し、村井邦彦が作曲したこの曲は、自由と夢をテーマにしています。
にじいろ
絢香が歌うこの曲は、未来への希望と自分自身の成長を描いた歌詞が特徴です。
2年生におすすめの曲
COSMOS
桜井和寿が作詞・作曲したこの曲は、広がりのあるメロディーと宇宙をテーマにした歌詞が特徴です。
HEIWAの鐘
福島県郡山市で生まれたこの曲は、平和への願いを込めた美しいメロディーが印象的です。
大切なもの
松本俊明作曲のこの曲は、友情や家族などの大切なものについて歌った感動的な曲です。
3年生におすすめの曲
手紙 〜拝啓 十五の君へ〜
アンジェラ・アキによる曲で、自分への手紙というテーマが斬新です。
YELL
いきものがかりの曲で、別れと未来へのエールをテーマにしています。
旅立ちの日に
卒業ソングとして広く親しまれている曲で、未来への希望を歌った歌詞が特徴です。
合唱コンクールの成功に向けて生徒へ伝えたい話
- 合唱コンクール当日の通信
- 成長するには現状を捨てるしかない
- 集団をよくするのがリーダー
- 合唱コンクールを成功へ導くために!
- 楽しさとは?
- 合唱コンクールの目的を伝え続ける
- 合唱コンクールの目的とは?
- 合唱の質を上げるには日常の質を上げる
- 目標を達成する組織づくりの考え方
合唱コンクールに向けて本気になった生徒の日記
合唱コンクールには、ドラマがあります。
生徒が本気になってくると、合唱コンクールで見違えるほど成長します。
以下は、最優秀賞を第一に考えるのか、
それとも、楽しさを第一に考えるのか、
学級で話し合った感想です。
生徒の日記
私は今回の話し合いでみんな最優秀賞をとりたくないのかな?
と思いました。
本当にとりたいなら楽しみなんて捨てると言ってくれるものだと思っていたけど、楽しみも必要だと言っていて、そもそも楽しむことも必要だと考えている時点で最優秀賞をとる気があるのかすごく疑問に思いました。
楽しむというのを少しでも入れるということは保険をかけておくことと同じではないでしょうか?
もしとれなくても楽しんでやれたからいいやと思いそれで済ませることができるし、少しぐらいふざけてもよいという保険です。
本気でとりにいくのに保険なんて必要なのでしょうか?
そして、楽しくやった方が思い出になると言っていました。
でも、去年の合唱コンの練習が思い出に残っていますか?
私はそこまで残っていないし、賞をとることができなくて悔しかったということぐらいしか思い出に残っていません。
だったらすべてを全力でやった方がよいと思います。
たかが数分の楽しさと、これからずっと心に残る最優秀賞。
どっちに価値があるのでしょうか?
私はもちろん最優秀賞だから、今日楽しさなんてすべて捨てて全力でやりたいと言いました。
去年もう少し頑張ればと思ったから、今年こそというはという思いで言ったのに、このままだと最優秀賞なんてとれないと思いました。
私の意見に〇〇さんがぴりぴりした空気ではやりたくないと言っていました。
私もそういう空気になるのは嫌です。
でも、それはお互いの意見があるからなることだし、何か問題があるときになると思います。
だから、それが嫌だからといってそういう空気を避け続けると、それも最優秀賞から離れてしまう行為なのではないでしょうか。
あと、ずっと楽しみなしだとつらいと言っていたけど、そういう考えを前提に話すのは遠まわしにやりたくないと言っているのと同じだと思いました。
確かに楽しみがなかったらつらいです。
でも、目先のことばかりにとらわれずに、もっと先の最優秀賞のことまで考えるとそんなこと捨てて、全力でやらないといけないと思いました。
最優秀賞と楽しいを両立させることはできません。
だから、どちらの方が大切なのか一度聞いてみたいです。
みんなが最優秀賞をとりたいと思っていたら楽しいを捨てないと確実にとれないし、楽しいをとるなら最優秀賞を捨てなければいけません。
本当にとりたいなら今のみんなの考えでは他のクラスも頑張っているのにそれでとれるなんて甘いものではないと去年のことを思い出してもう一回考えてほしいと思いました。
この感想を、学級の全員に紹介しました。
練習に楽しさが必要かどうかの正解は分かりませんが、本気になれる生徒が、合唱コンクールでは、必ず出てきます。
他にも、
「指揮をしていても楽しくない」と指揮者に言わせてしまうような練習をしていた自分が恥ずかしいです。
「こんなものでしょ」と思わせてしまっていた自分の練習態度も恥ずかしいです。
話し合いでは、「楽しくなかった」とか「やりたくなかった」とか、聞いていて苦しくなるような言葉がたくさんありました。
きっと言ってくれた人は、もっと苦しかったんじゃないかと思います。でも、その苦しさよりも、きっと「このクラスで最高の歌を歌いたい」という思いが勝ったのだと思います。
仲間を信じていなければ、本当のこと、特に言いづらいことなんて言えなかったでしょう。
4月からたくさんの行事をこの仲間と乗り越えてきました。
応援合戦も、この仲間だったからこそ、本当に素晴らしいものを作ることができました。そんなクラスだからこそ、練習が始まった頃、中学最後の合唱をこの仲間と歌えることが幸せだと思っていたのに、その気持ちを忘れてしまっていました。
まだ練習はあります。
自分にできることがあります。
本音を言ってくれた仲間、その言葉を受け止めてくれた仲間のためにも、できることを全部やって本番を迎えたいです。
そんな本気になった生徒だからこそ、合唱コンクール本番では、以下のような思いになれるのです。
3年生の合唱は、この合唱コンクールで終わりなので、みんなすごく頑張っていて、優勝したいという気持ちが強く伝わってきました。
どのクラスもとても上手でした。
クラスごとの工夫も感じられ、リズムに乗って体を揺らしたりする姿を見て、聞いて、とても感動しました。いよいよ私たちの番が来たときは、とても緊張しました。
舞台に上がるときも足が震えていましたし、声がちゃんと出るかどうかとても不安でした。
でも、台に上がったときに〇〇が笑ってくれて、「大丈夫、いつも通りに」と思い、私も笑顔になれました。
しかし、やっぱり高い音のところでは声が出なくて悔しかったです。
でも、隣にいる〇〇の声を聞いたら、なんだか元気になれました。
強弱や指揮者に言われたことをみんながちゃんと意識して歌えていたと思います。結果発表のとき、みんな手を合わせてすごくドキドキしていました。
6組が呼ばれた瞬間、すごく嬉しくてみんなで泣きました。
でも、優勝できなかったクラスの子たちはすごく悔しいと思うので、その分の思いも受け止めたいと思います。
優勝できたのは、今まで頑張ってきたクラスのみんなや先生のおかげなので、本当に感謝したいです。
ありがとう!!また、このクラスでの一つの思い出になりました。
合唱コンクールを通してみんなのいろいろなことを知ることができ、みんなの意見を聞いて考えることができました。
本当にいい経験になったと思います。
6組らしい歌を歌えたので、それが一番です。
これからも6組でいろんなことをやっていきたいです。
また、心を一つにして。
6組、大好きです。
また、合唱コンクールで賞を獲ることができなくても、
合唱台に立つと、4組で頑張ってきたことや心がけたことを思い出していました。
また、4組の世界にいると感じることもできました。
指揮者が指揮を振って伴奏がスタートし、いつものように一つ一つの言葉を大切に歌うことができました。
強弱もとてもいい感じになっていました。体も自然に動いていました。
最後の最後まで、声、強弱、心…悔いの残らない合唱になったと思います。自由曲の「道」は卒業の曲なので、今までやってきたことや4組のことを考えて歌いました。
歌が始まってすぐに泣いている人がいました。
その姿を見ていたら私も泣きそうになりました。でも、ここで泣いたら声が出ないと思い、我慢しました。
きっと声は震えていたと思います。
心がなければ、ここまで感情が入ることもなかったのではないでしょうか。
歌っていてこんなに気持ちが高まったのは今回が初めてでした。
音程が違ったところもありましたが、歌い終わったときには、とても満足していました。結果発表で最優秀賞の発表があり、5組が呼ばれたときは、一瞬何も考えられませんでした。
でも、5組の合唱には鳥肌が立ちました。結果は優勝ではありませんでしたが、8組の一人一人が優勝に向かって必死に練習に取り組むことができたので、悔しいというよりも達成感があります。
本当にこの4組でよかったと思います。
こう思えることが幸せです。
今日は今までで一番心に響くような8組の合唱ができたと思います。
私は、4組の合唱が一番だったと思っています。
4組最高―!!
合唱コンクールが終わった後の先輩の感想は、合唱コンクールの練習のスタートに、生徒へ読ませたいですね。
おすすめの本
おわりに
合唱コンクールは、生徒たちの努力や協力の成果を発表する素晴らしい機会です。
この記事で紹介したポイントを活用して、教師としての指導力を高め、生徒たちと一緒に素晴らしいパフォーマンスを実現しましょう。
合唱コンクールを通じて、生徒たちが音楽の楽しさや達成感を感じ、次のステップへと成長することを願っています。