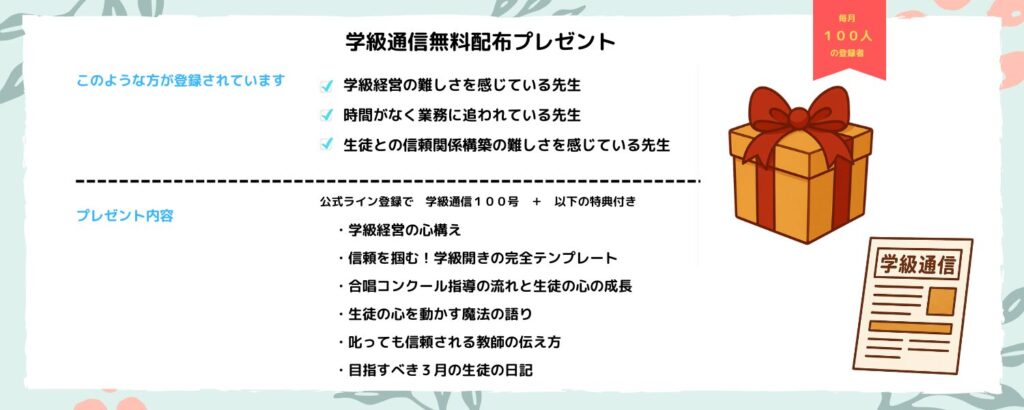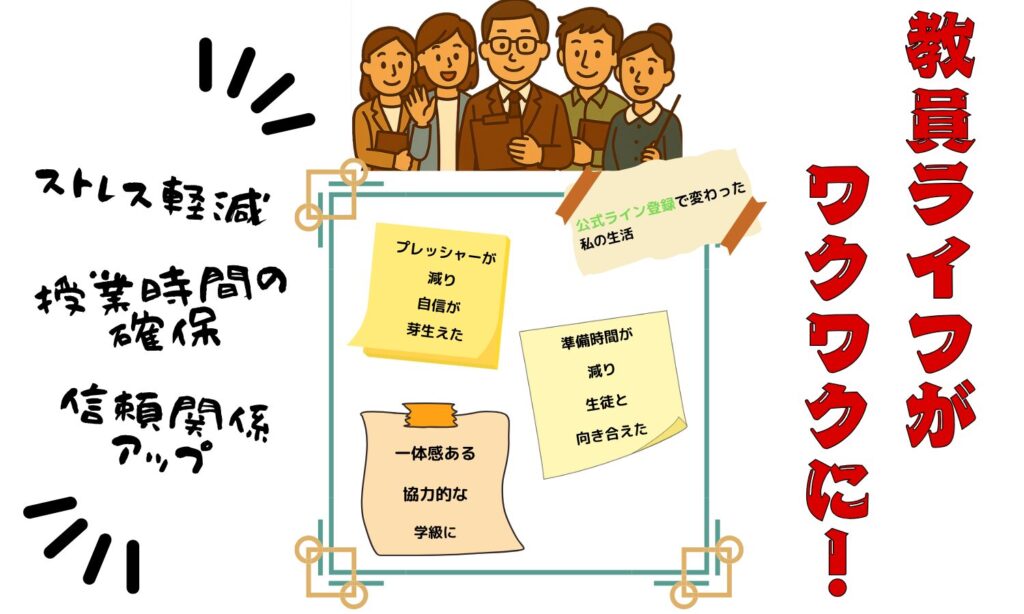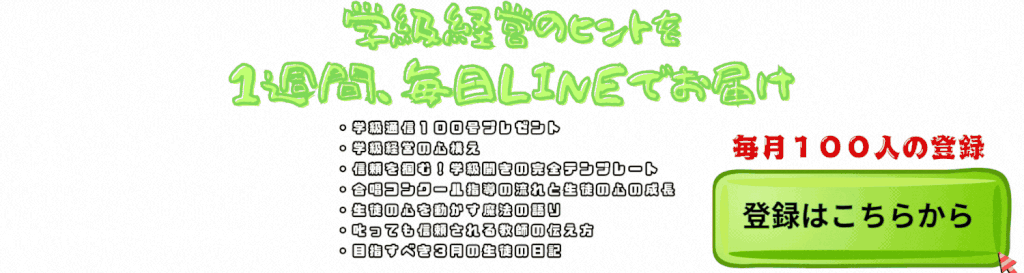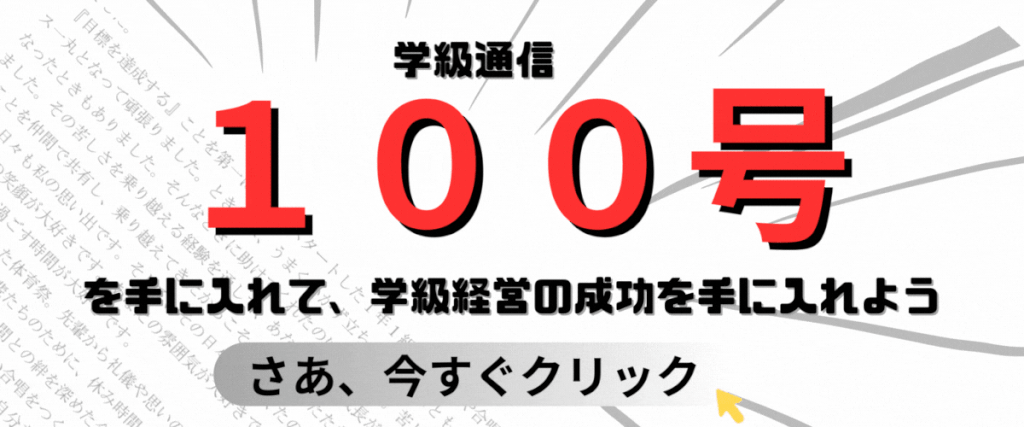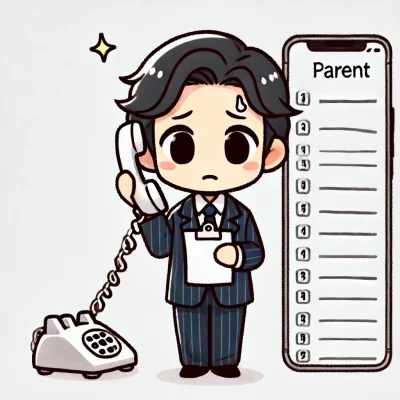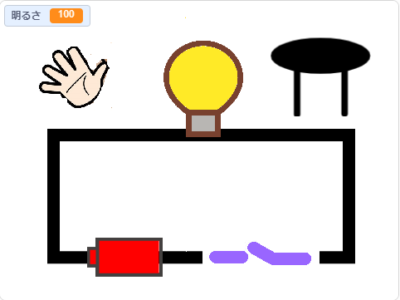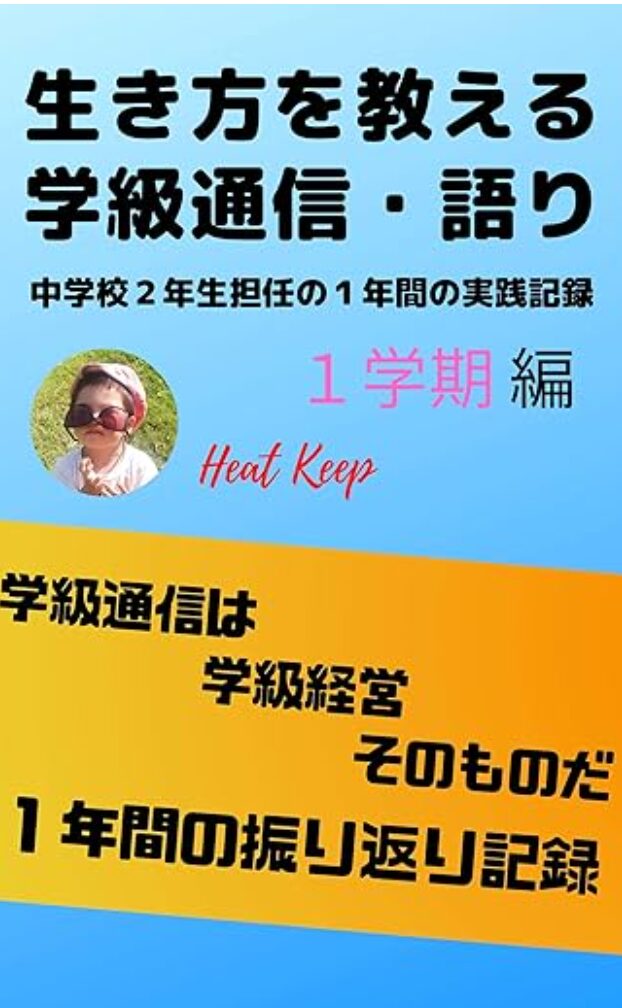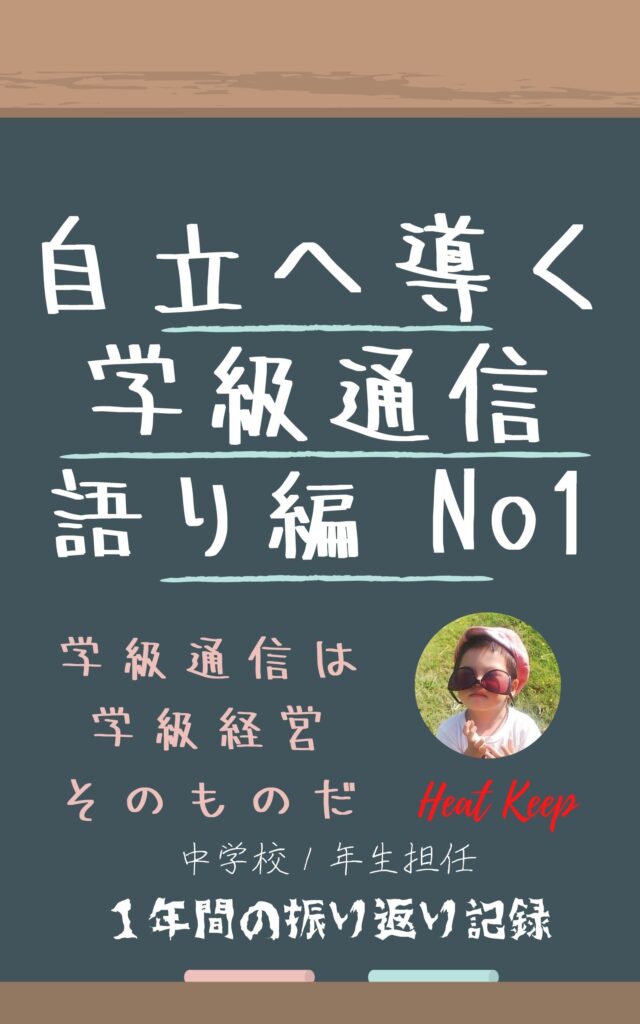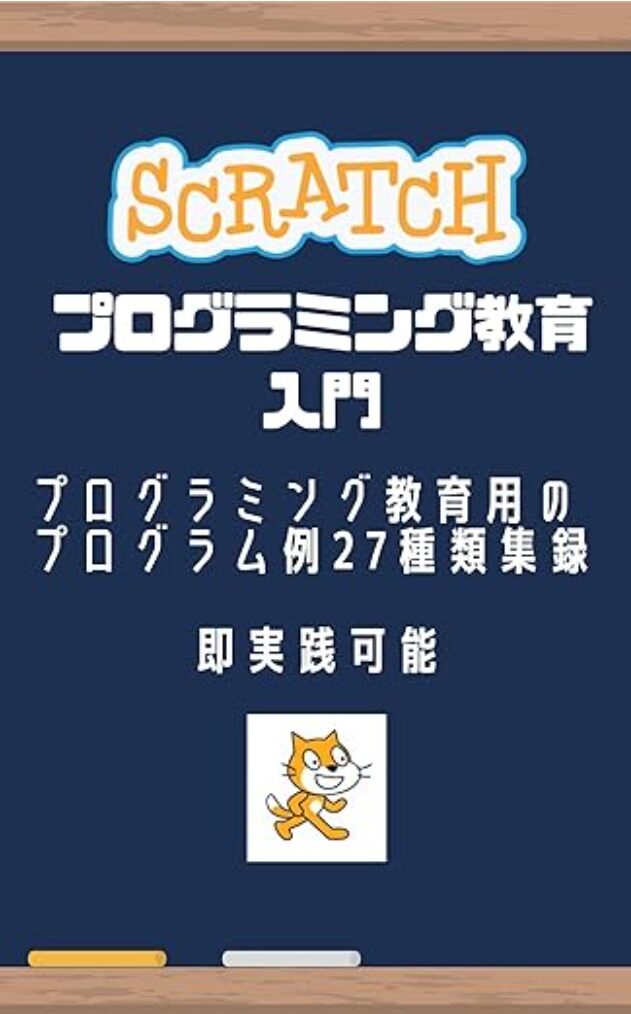はじめに
学校生活の中で、生徒総会は生徒の意見を反映し、学校の改善に貢献する重要なイベントです。
しかし、多くの生徒や生徒会担当の教員にとって、総会の準備や進行は大きなプレッシャーとなります。
この記事では、生徒総会を成功させるための効果的な準備方法や運営方法を紹介します。
まず、生徒総会の目的や意義について理解を深めることから始めましょう。
次に、具体的な準備ステップと必要なツールを紹介します。
この記事を読むことで、総会の進行がスムーズになり、実りある生徒総会をつくるためのヒントが得られるでしょう。
クリックできる目次
生徒総会の意義と目的
生徒の意見を反映する場
生徒総会は、生徒が自分たちの意見や提案を発表し、共有する場です。
これは学校運営において生徒の声を重要視する姿勢を示し、全員が積極的に学校生活に参加するきっかけとなります。
問題解決のための話し合う場
総会では、現在の問題点や改善点について話し合うことができます。
半年間を振り返りどこが成長したのか、
そして、今後、どのように成長したいのかを話し合う場になります。
これにより、生徒同士が協力して解決策を見つけることができ、学校環境の向上につながります。
準備ステップ
1. 目標設定
総会の目標を明確にすることが第一歩です。
例えば、「生徒会の活動報告を行う」、「新しい提案を発表する」、「現在の問題点を議論する」など、具体的な目標を設定しましょう。
2. 課題作成
議題を作成し、参加者に事前に共有することが重要です。
これにより、全員が議論する内容を把握し、意見を準備することができます。
事前に、プチ生徒総会を各学級で行っておくと、議題が盛り上がったり、会の進行がスムーズになります。
3. 役割分担
総会の進行役、記録係、タイムキーパーなどの役割を事前に決めておくことで、当日の進行がスムーズになります。
それぞれの役割に適した生徒を選び、リハーサルを行うと良いでしょう。
議長
総会を進行し、議題を取りまとめる役割です。
議論の進行を管理し、時間内に議題が終わるように調整します。
副議長
議長を補佐し、必要に応じて議長の代わりに総会を進行します。
また、議長がいない場合にその役割を引き継ぎます。
書記
総会の記録を取り、議事録を作成します。
議事録には、議題の内容、発言内容、決定事項などが含まれます。
タイムキーパー
各議題の時間を管理し、予定通りに議論が進むようにします。
議論が長引く場合には、議長に知らせて調整を促します。
発言者
自分の意見やクラスの意見を代表して発表する役割です。
発言者は、事前に意見を整理して、原稿を準備しておくとよいでしょう。
質疑応答担当
発言内容に対して質問を受け付け、回答する役割です。
質疑応答を円滑に進めるために、予め想定される質問と回答を準備しておくと良いでしょう。
運営委員
総会全体の運営をサポートし、必要な物品や資料を準備する役割です。
運営委員は、総会前後の準備と片付けも担当します。
4. 資料準備
議題に関連する資料やデータを準備し、参加者に配布します。
生徒総会の2週間前に議題を配付し、クラスごとに話し合いの場(プチ生徒総会)を設けます。
ゆとりをもって、資料を準備することで、生徒からの意見や質問を事前に集め、整理しておくことができます。
プチ生徒総会とは?
プチ生徒総会は、生徒総会の議題について各学級で事前に話し合う場です。
これにより、生徒たちは自分たちの意見を整理し、他の生徒と意見交換を行う機会を持つことができます。
プチ生徒総会は、クラス全員が参加しやすく、意見を出し合うことで、多様な視点を共有しやすくなることが特徴です。
意見の多様性
プチ生徒総会を通じて、多様な意見が出され、より幅広い視点から議題を考えることができます。
議論の深化
事前に意見交換を行うことで、生徒総会当日の議論がより深まり、具体的な解決策を提案しやすくなります。
生徒の主体性の向上
自分たちの意見が総会で取り上げられることで、生徒の主体性や責任感が育まれます。
生徒総会の具体的な進行方法
1. オープニング
司会者が総会を開会し、議題と進行スケジュールを確認します。
- 開会の挨拶: 司会者が生徒総会を開会する宣言をし、参加者に挨拶します。簡単な挨拶と総会の目的を述べ、参加者の意識を統一します。
- 議題の確認: 本日の議題を明確にし、ホワイトボードやプロジェクターを使って全員に見えるようにします。
- 進行スケジュールの説明: 会議の流れを簡単に説明し、各セッションの時間配分を確認します。
2. 議題の説明
議題についての背景や現状を説明します。
ここで資料やデータを活用し、生徒が理解しやすいように工夫します。
- 背景情報の提供: 議題に関連する背景情報や問題の現状を、資料やデータを用いて説明します。生徒が議題の重要性を理解しやすいように、具体的な事例や統計データを示すと効果的です。
- 資料の活用: 配布資料やスライドを使いながら説明します。視覚的な資料を用いることで、生徒の理解を深めます。
- 質疑応答: 資料の説明後、生徒からの質問を受け付けます。疑問点を解消し、議題に対する理解を深めます。
プチ生徒総会で出された意見を伝えます。
3. 意見交換
各生徒が順番に意見を述べる時間を設けます。
全員が発言できるよう、司会者が発言の機会を公平に指名します。
- 順番決め: 予め発言の順番を決めるか、発言希望者を募ります。全員が公平に発言できるように配慮します。
- 発言時間の管理: 各生徒の発言時間を決め、タイムキーパーが時間を管理します。なるべく多くの生徒が発言できるように配慮しましょう。
- 仲間の考えについて感想を述べる: 発言後に、他の生徒から簡単な感想をもらう時間を設けます。この感想をもとに、話し合いへとつないでいきます。
4. 話し合い
意見交換の後、話し合う時間を設けます。
生徒が自分の意見を出し合い、議題について深く掘り下げます。
司会者は、話題が脱線しないように適宜軌道修正を行います。
- 話し合いのテーマ設定: 意見交換で出た意見を元に、話し合いのテーマを設定します。プチ生徒総会で出された意見を参考に、事前に考えておくとよいでしょう。
- 少人数グループでの議論: 大人数でのディスカッションが難しい場合、少人数のグループに分けて議論を行います。
- 司会者の役割: 司会者はディスカッションの進行をサポートし、議論が脱線しないように適宜修正します。また、全員が発言できるように配慮します。
5. 合意形成
意見の整理
- 書記の役割: 書記がディスカッション中の意見を整理し、要点をまとめます。
- まとめの発表: 書記がまとめた意見を全員に発表し、確認します。
投票または合意
- 投票の実施: 必要に応じて、意見をまとめた後に投票を行います。
投票結果を基に、最終的な合意を決定します。 - 全員の意見を反映: 投票の結果が平等に反映されるようにし、少数意見も尊重ができるとベストです。
決定事項の確認
- 決定事項の確認: 合意に至った事項を全員で確認し、次のステップについて説明します。
これにより、生徒総会の結論を必ず明確にしてから終わりましょう。 - 今後の説明: 今後の動きについて説明し、誰がどのような行動を取るかを明確にします。
6. 振り返り
振り返りの時間
- 振り返りの実施: 総会終了後、全員で振り返りの時間を設けます。
生徒総会での決定事項について、自分自身ができることを用紙に記入させます。
アンケートの実施
- アンケートの配布: 総会の運営や内容についてのアンケートを実施します。
生徒たちの率直な意見を収集できたり、生徒総会の時間が足りず発言できなかった生徒の意見も収集できます。 - アンケートの活用: アンケート結果を基に、次回の総会に向けた具体的な改善策を決めていきます。
スムーズな進行をサポートするツール
生徒総会をスムーズに進行するために活用できるものについて紹介します。
ホワイトボード
-
議題の掲示: 総会の議題や進行スケジュールをホワイトボードに書き出し、全員に見えるようにします。
-
意見の整理: 生徒の意見やディスカッションのポイントをホワイトボードにまとめることで、視覚的に整理できます。
-
タイムラインの作成: 各議題の時間配分や進行状況を表示し、時間管理に役立てます。
プロジェクター
-
資料の共有: 議題の説明やプレゼンテーションをプロジェクターで投影し、全員が同じ資料を見ながら議論できます。
-
リアルタイムの修正: パソコンで作成した資料や議事録をリアルタイムで修正・更新しながら共有することができます。
フリップチャート
-
アイデアの可視化: ディスカッション中に出たアイデアや意見をフリップチャートに書き出し、全員が見えるようにします。
-
簡単な持ち運び: 軽量で持ち運びが簡単なため、教室や会議室を移動してもすぐに使えます。
ポータブルPAシステム
-
音声の拡張: 大きな教室やホールでの総会でも、ポータブルPAシステムを使って司会者や発言者の声を全員に届けることができます。
-
マイクの活用: ワイヤレスマイクを使えば、発言者が自由に移動しながら発言できます。
タイマー
-
時間管理: タイマーを使って各議題や発言時間を管理します。目に見える形で時間を設定することで、効率的な進行が可能になります。
ポスターボードと付箋紙
-
意見の可視化: ポスターボードに付箋紙を使って意見を貼り付け、視覚的に意見を整理します。
-
グループワーク: グループディスカッションで出た意見をまとめるのに便利です。
レーザーポインター
-
指示の明確化: プロジェクターで投影した資料やホワイトボードの内容を指し示すのに役立ちます。議論のポイントを強調しやすくなります。
モバイルホワイトボード
-
移動可能なボード: 移動可能なホワイトボードを使えば、必要に応じて教室や会議室内のどこでも設置できます。ディスカッションの流れに合わせてボードを動かすことができます。
ディスプレイモニター
-
デジタル資料の表示: パソコンやタブレットを接続して、デジタル資料やリアルタイムの情報を表示します。
-
ハイブリッド会議: オンライン参加者がいる場合は、ディスプレイモニターを使って映像や資料を共有することができます。
おわりに
生徒総会を成功させるためには、綿密な準備と効果的な進行が欠かせません。
この記事で紹介した方法を参考に、ぜひ次回の総会を成功させてください。
全員が満足し、建設的な議論が行われる総会は、学校生活をより豊かにする大きな一歩となるでしょう。